得意分野をウリにしたシナリオ制作~自分のスタイルを確立する
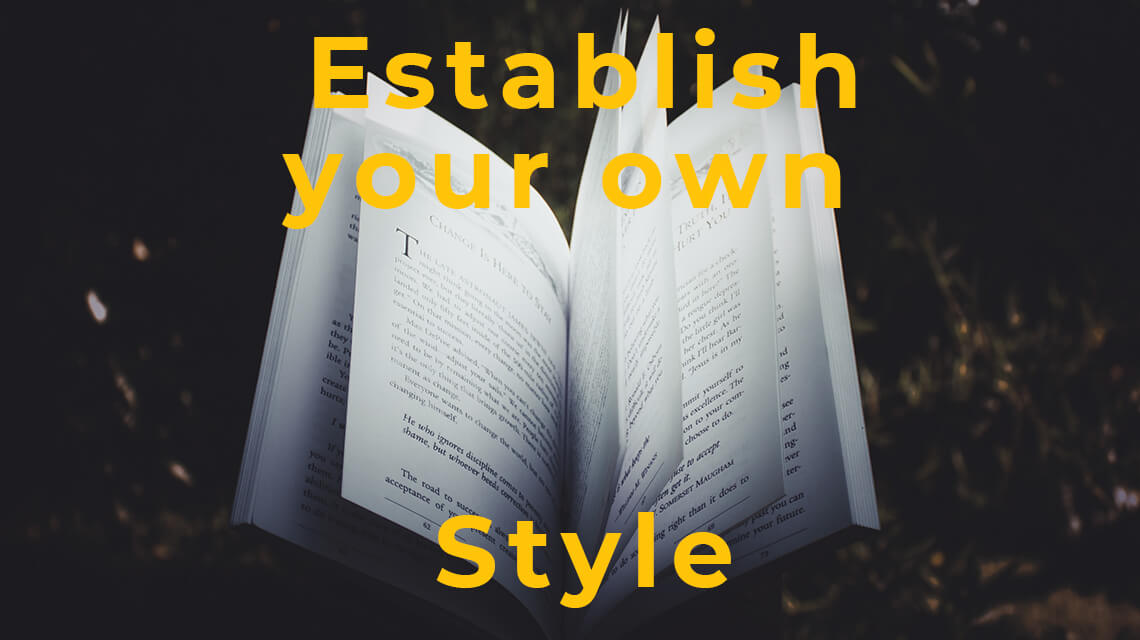
シナリオ制作をする上で自分のスタイルを確立することは非常に重要です。
つまりは自分の得意パターンを作り上げるということです。
たとえば、作家や脚本家の名前を聞いたときに意識せずとも作品のジャンルが想像できることはありませんか?この人が脚本のアニメならばハードなSFモノに違いないとか、あの人の小説ならばジュブナイルだろうなだとか。
クリエイターの名前から作品の概要が連想できれば、それはその人のスタイルが確立されていると言えます。
自分のスタイルを確立するために
これからシナリオ制作の仕事を始めたいと思っている方は、習作として作品を執筆する上で、自分の好きなジャンルやいままでに読み込んできたジャンルを題材に選ぶことが多いのではないでしょうか。
シナリオ制作の手法を練習するために、書きたいものをたくさん書いて数をこなしていくことは、シナリオの作法の会得、フォーマットの習熟につながります。
書きやすい題材を書くことでさほど苦労をせずに数をこなすことができますので、まずは筆を執ってみるべきです。
「書きたいもの」と「書けるもの」は違う
執筆する上で意識すべきは「書きたいもの」と「書けるもの」は違うということです。
では、具体的に「書きたいもの」と「書けるもの」の違いを理解するためにはどうしたらよいのか。
ひとりで自分の書いた作品を読み返してみたところで、それは主観的な感想に過ぎません。「書けるもの」であるのかどうかが判断できません。
作品を公開して他人の批評を得る
まずは自分の作品を世の中に放ってみましょう。作品を公開して他人に読んでもらうのです。
小説投稿サイトもありますし、Amazonの電子書籍で自費出版も容易にできるようになりました。
様々な人間の批評が最も客観的な理解に繋がります。
他人に批評してもらうことは、とても勇気のいることです。
「書きたいもの」と「書けるもの」がイコールであれば、作品の評価は着実に上がります。反して、思うような評価が得られず、批評も厳しい意見が多数を占める場合は、そのジャンルは現段階で「書けるもの」のレベルに達していないということでしょう。
得意ジャンルを伸ばす
仕事としてシナリオ制作を請け負う意向であれば、まず「書ける」ジャンルを伸ばしていくのがより近道です。
自分のスタイルを確立することは自分をブランド化することと同義です。強みを持つことで自己アピールもしやすくなります。
実際に私どもがライターに執筆を依頼する場合は個々の得意ジャンルを必ずチェックします。
ジャンルによって展開や言い回し、背景の描写、キャラクターの引き立たせ方などの技法はそれぞれ異なります。そしてその技法は一朝一夕で身につくものではありません、経験とセンスが問われます。
専門分野はライターの強い武器になります。
展開のスタイルを確立する
書けるジャンルが把握できたら次の一手は展開のスタイルの確立です。
展開の制作では、自身がいままでに読んできた本や観てきた映画などの経験の影響が色濃く出るものです。
自分ではオリジナルの展開を作っているつもりでも、客観的に見てみると「どこかで見たシーン」になってしまうことも儘あります。
しかしオリジナリティを出すあまり、奇想天外な展開を無理やり入れ込んで支離滅裂な脚本になってしまっては本末転倒です。
そこでまずは作りやすい展開をいくつか書いてみて、その展開をブラッシュアップしていくことをおすすめします。
そうすることで、その展開では他に引けを取らない、展開のエバンジェリストを目指すことができます。
展開の引き出しを増やす
たとえば、荒木飛呂彦や冨樫義博のお話であれば、伏線を散りばめてきっちり回収する展開に長けているし、村上春樹であれば、複数のシナリオを同時進行させてそれをひとつに集結させる展開が高く評価されています。
とはいえ、作りやすい展開ばかりを書いていくと、早々にマンネリの壁にぶち当たるのも事実です。それを解消するには、とにかく他者の展開の型をたくさん吸収するしかありません。
展開の引き出しを増やすには、たくさんの映画を見て、たくさんのドラマを見て、たくさんの漫画を読んで、たくさんの小説を読むということです。
また、既存のシチュエーションを自分の作品に取り入れるのであれば、コンテンツのジャンルやキャラクター性に沿うように最適化することは必要不可欠です。
たとえばゲームのシナリオに、インスピレーションを受けた映画の展開を用いるのであれば、ゲームを盛り上げるための演出にアレンジが必要ですし、用いる展開が登場するキャラクターの性格や行動、バックボーンに沿っていなければユーザーは違和感を感じることになります。
有限の展開を自身の作品にいかに落とし込むかが重要です。
キャラクターのタイプを確立する
ジャンル、展開と続き、最後はキャラクターのタイプのお話です。
いくつか物語を書いているうちに、意図せずキャラクターが似通ってしまったり登場人物がワンパターン化してしまうことは、誰しもが一度はぶつかる壁なのではないでしょうか。
では、キャラクタータイプの引き出しを増やすためにはどうしたらいいのか。
まず、自分が作るお話は、結局は人生における経験からしか生まれません。
つまりは人生でどれくらい多くの人間と出会い、言葉を交わしたのか?
その人をどのくらい深く観察できた(=知った)のか?
すなわち、自分がいままで「人とどれだけ関わったか」がキャラクターの引き出しの数になるということです。
ただし、生きたキャラクターを生み出すために自分の経験を掘り起こすという作業は、時に辛く苦しい工程になるかもしれません。
自分のトラウマや思い出したくない出来事、そういった悲しい過去を掘り起こして紡いでいくプロセスが必要になる場合があるからです。
しかし、自身の経験から紡がれた物語には強烈なリアリティーと説得力があります。
空想だけで描いたお話は、どこか空虚さが見え隠れしてしまうことが多く、読者を惹きつけるだけの魅力に乏しくなりがちです。
読み手を惹きつけるには
登場人物に感情移入できる、つまりは日常生活に登場しそうなリアリティのあるキャラクターでないと、読者は「そんなやついないよ」という感想で終わってしまいます。
たとえば小説や漫画を読んでいて、このキャラクターは中学生の頃に尊敬していた先輩に言動が似ているから応援したくなる、あのキャラクターは苦手な上司に性格がそっくりだから苛々するなど、実在する誰かになぞらえて特徴付けしていることはありませんか。
読者を惹きつける人物描写をするためには、キャラクターのパターンを増やす=人と沢山知りあい、性格や行動原理の引き出しを増やすことが肝要です。
もちろん、映画や漫画、ドラマや小説など、たくさんの作品に触れてパターンを増やしていくのも方法のひとつですが、現実の友達や知り合い、身近な人たちをベースにしたキャラクター造形を心掛けることで血の通ったキャラクターが作りやすくなります。
同時に、書き手側の書きやすさにも繋がります。
知った人の行動ですから、次にこのシーンに登場した場合にどういう行動をするのか?というのは想像しやすいのではないでしょうか。
まとめ
シナリオ制作においての自己スタイルの確立をテーマにお話してまいりましたが、まだまだお伝えしきれていないことや著者が勉強しなければならないことは沢山あります。
今回は主に得意を伸ばすというお話でした。まずはみなさんにシナリオ制作という創作活動を楽しみながら続けていただきたいという思いで書きました。
シナリオ制作にご興味をお持ちの方は、お気軽にページ下部のCONTACTよりご連絡ください、スタッフ一同お待ちしております!